《愛の火》

不覚時代、初めて『クリスマス・キャロル』を読んだ時に、描かれている世界は当時イギリスにあった“普通”のクリスマスなのだと勘違いし、「へぇ〜さすが本式は凄いや」と思っていた。
ところが、実際にこんな感じでクリスマスが祝われ出したのは、この作品が出版されてからなのだと言う。
イギリスのクリスマス習慣は17世紀の清教徒革命で、異教的だと一旦やっつけられて凹まされ、王政と共に息を吹き返した所で18世紀の産業革命に再びペシャンコにされて、19世紀には大分廃れていたらしい。

だが丁度この時代、産業革命のもたらした拡大の歪みに疲弊した社会が、内なるエンストを起こしかけてもいた。
外側の天候だって曇るわ寒いわで、実は誰も彼もが火起こし待ち。
しかし、何もなしに愛し愛されるって、不覚にとってはえらく難しい。
そこに
「この時ばかりは愛し愛され祝い祝われましょうや」

と年末行事に託した火起こしの提案が、物語の形で舞い込んだ。
大ヒットした本作を読んだ人々が、七面鳥を買いに走り、歌を歌い、プディングを作り、寄付をし、やんやかやんやかやり出したことで、描いたクリスマスに実際のクリスマスが追いついた。
『クリスマス・キャロル』は愛の火を起こして、クリスマスそのものを晴れやかに再創造した作品。
ディケンズはイギリスにおけるクリスマス復興の功労者であると言われている。

今や世界規模のひょっとこ大祭となったクリスマスではあるが、派手な現代のクリスマスに霞むことなく、『クリスマス・キャロル』は変わらず輝いている。
何故この物語がこれ程までに人々の胸を打ち、2017現在まで愛され続けているのか。
時代を超えて皆が奥底に持つ、愛ある行いをしたい気持ちが、火起こしされるだけではない。
この物語が、
最も変化しなさそうな人物の変化

を描いて、それを実現させているから。
愛のない行いを積み重ね、肉体には皺が寄り根性は捻じ曲がり、世間を蔑んで生きている男。
彼が変わるなら、誰だって変わる。
そう思わせてくれる存在が変化していく様を観ながら、読み手は自身の変化の呼び起こし、愛の火起こしを内側に感じるのだ。
スクルージも又、ひょっとこである。
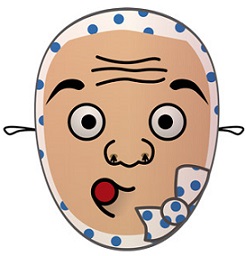
読んでいて「ここに起きているのは真の変化だ」と感じたのが、幽霊達との旅を終えて目を覚ました彼が
優れた人物になっていない点
スクルージの意識は、まるで産まれたばかりの様にまっさらになってしまう。
原作からセリフを挙げてみると、
“「羽みたいに軽くて、天使みたいに幸せで、小学生みたいに愉快な気分だ。
酔っぱらったみたいに頭がくらくらするぞ。
みなさん、クリスマスおめでとう!
そして、よいお年を、世界中の皆さん!
ワーイ!ヤッホー!ワーイ!」”

特定の誰かじゃなく、世界中に愛を発している。
この後小学生から更に新しく、彼の意識は丸裸になる。
“「幽霊さん達とすごしているあいだに、どれだけ時がたったのやら!
さっぱりわからん!赤ん坊も同然だわい!
いや結構。かまわんとも。赤ん坊、大いに結構。
ワーイ!
ヤッホー!
ワーイ!」”

このワーイ!ヤッホー!ワーイ!に、確たる実感が全て現われている。
内なるワーイ!ヤッホー!ワーイ!の光は意識に灯り続け、この後周囲に弥栄な行いとなって波及していく。
弥栄は、知性や能力を鍛え上げて成される訳ではない。
知性や能力は基盤の上に自然発生するもの。
そして基盤には只、愛と歓びがあるのみなのだ。

スクルージは、それまでの自分像を超える大変化を、過去現在未来と区分けされたあらゆる今を見つめ、死をも通過することで見事にやってのけた。
彼が全存在をかけて成した大きな“ひっくり返り”を読者や観客は追体験し、転換によって生まれる未知の風を一緒に感じる。
この物語自体が、無明の苦しみから意宣りと目覚め、そして愛の発現までを通して味わう、一種の胎内巡りとなっている。
何かと理由をつけて、自らに限界を定めてしまいがちな方が居られたら、一度しみじみと作品に触れて『クリスマス・キャロル』トンネルを通り抜けてみられることをお勧めする。

入って出ると、違うもの。
(2017/12/21)



