《生まれる言葉》
「理想」の語源について調べた所、この表現が初めて使われた場面に行き当たった。
J・S・ミルの著作を訳した『利学』の中で、訳者である啓蒙家の西周が考案した造語だとする解説を発見。
と言うことは、それより前は日本人の生活に理想は影響を与えていなかったのだろうか。
それ以前に人々の意識に影響を与えていた、理想に近いものを挙げるとすれば「徳&罰」と言うセット概念がある。

信心深い人々にとっては現代でもお馴染みの、
「良いことである徳を積むと罰を免れますよ」
と言う、世界観を支えているコンビだ。
そこから、近代的になろうぜと脱皮を図る時に、理想は必要な起爆剤だったのかも知れない。

只、何にしても区別をつけて目立たせるのに、“じゃない方”を作りたがるのが人間の癖。
そして何でか、理想のじゃない方に現実を持って来たから、話はもっとややこしくなった。
ややこしくして入り組んだ不覚体験を重ねるのが、その時点で虚空がやりたかった事なので、これはこれで何も問題はない。
プロブレムと言う意味での問題は、申し上げて来た通り、特に無いのだ。
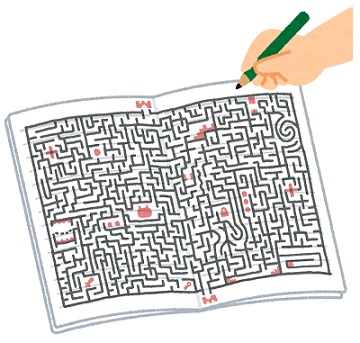
順当にややこしく入り組み、順当にこんがらかり、順当に身動きが取れなくなって、その中から
「あれれ、何しに物理次元に来たんだっけ。あ、そうだ!」
と、原初の記憶が蘇る端末が出て来る。
何も問題はない。
理想の語を生んだ西周は、他にも色んな言葉を造っている。

「哲学」「真理」「芸術」「理性」「科学」「知識」「定義」「概念」「命題」「心理」「物理」「消費」「取引」「帰納法」「演繹法」「権利」などなど。
普段の生活で当たり前に使っている言葉も、初めからあった訳ではなくこうして誰かを通して、頃合いに生まれて来ている。
そしてその言葉が切っ掛けで、ものの見方が変わったりする。
面白いことである。
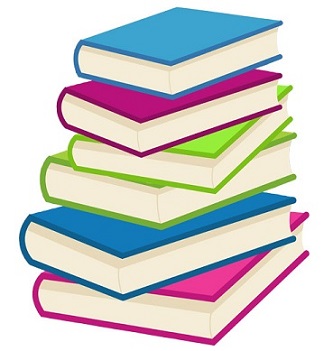
見方変われど、そこに在るもの。
(2025/6/12)
